■ワークショップ 2005.8/20-27
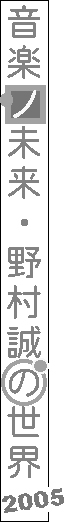
■プレイベント(映像上映会)
2005年8月28日(日)
13:00〜13:45(開場 12:50)
野村誠+野村幸弘による映像作品
「だいんだいん」 (2004年ワークショップ作品の映像)
「ドゥスン・ゲダレンのあぜ道」 (インドネシアで撮影)
■コンサート
2005年8月28日(日)14:00開演
■会場
碧水ホール
|
■ワークショップ 2005.8/20-27 |
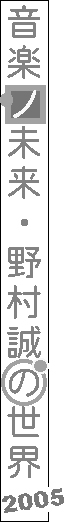
|
■プレイベント(映像上映会) 2005年8月28日(日) 13:00〜13:45(開場 12:50) 野村誠+野村幸弘による映像作品 「だいんだいん」 (2004年ワークショップ作品の映像) 「ドゥスン・ゲダレンのあぜ道」 (インドネシアで撮影) ■コンサート 2005年8月28日(日)14:00開演 ■会場 碧水ホール |

|
野村誠(作曲、ピアノ、監修) 柏木陽(俳優) 市川慎(箏) 菊地奈緒子(箏) 片岡祐介(打楽器) 林加奈(おもちゃ楽器) 石村真紀(ピアノ) |
ワークショップ参加の皆さん 赤羽美紀 飯山尚美 市居みか 高橋利恵子 高橋侑子 高橋真依子 畑佐好見 畑佐小晴 正木恵子 向久保恵美 向久保拓巳 村木幹也 村木基起 村木ナナコ 村木伽野子 山本雅史 協力:片岡由紀 |
|
1 くつがえさー音頭 片岡祐介さんの委嘱で、2005年の1月に作曲。2月に片岡祐介さん、岡崎香奈さんにより初演された。2000年の秋、片岡さん、岡崎さんと話していた時に、 「野村さんは、作曲という概念をくつがえしているわけでしょ?」 と岡崎さんが、「くつがえさー」という言葉をつくった。 ぼくは作曲という概念を「くつがえし」ているのかもしれないし、ずっと真面目に「作曲」ということを突き詰めているだけとも言える。真面目に突き詰めていくと、どうしても「くつがえす」べき壁にぶちあたったりして、「くつがえす」必要が出てきたりする。片岡さんは、何の「くつがえさー」なのだろう?岡崎さんは、何の「くつがえさー」なのだろう?とにかく、「くつがえさー」を応援するために書いた応援歌が、この曲。 マリンバとピアノのための作品だが、本日は音域の少ないマリンバとシロフォンを組み合わせるため、片岡さんには無意味に跳躍を強いています。 2 りす 箏の上で文字を書いたら、どんな音になるだろう? そんな疑問が、この曲の最初のコンセプト。文字を描く動きには、人それぞれのリズムがある。書道の音楽だ。ひらがなのリズム、カタカナのリズム、アルファベットのリズム、漢字のリズム、楷書のリズム、行書のリズム。 そうやって文字を音にすることを考えているうちに、曲のイメージが膨らんできた。でも、音を考えずに、指使いを考えた。調弦は演奏者に委ねたので、どんな音が出るかは演奏者によって全く違ってくる曲。 水谷隆子さんの委嘱で、2000年の春に作曲。ウェスリアン大学の講堂で初演された。 3 つみき 菊地奈緒子さんと市川慎さんの二人の委嘱で、二人のリサイタルのために作曲。 17絃の2面の作品。「つみき」のように、演奏家がパーツを組み合わせて形が作れるようにと考えて、15個の場面を作曲。演奏者は、このうちの全てまたはいくつかを選んで、好きな順番で演奏することができる。その場で即興的に順番を決めながら演奏してもいい。この曲を書いて、17絃という楽器と仲良くなれた気がしています。 |
4 押亀のエテュード 日原史絵さんの委嘱で、1997年7月に作曲。初めて書いた箏曲。箏のことは全然分からずに、まず、箏のCDを1枚聴きながら寝たところ、翌朝目が覚めた時に印象に残ったのは、「押し手」という奏法だった。その音色がたまらなかった。押し手だけで1曲作ろうと考えた。 5 improvisation 即興ピアニストの石村真紀さんとのデュオ即興です。石村さんは、音楽療法士として、発達障害児と非公開の即興演奏を15年以上続けてくる中で、自分なりの音楽を育ててきた人です。本日の演奏は、10分程度ということ以外は、何の決めごとのない即興演奏です。 6 パパとママ 柏木陽さん、林加奈さん、片岡祐介さん、市川慎さん、菊地奈緒子さんとの共同作曲作品。一昨日完成したばかりの作品です。全体は大きく分けて4つの部分から成っています。柏木さんが市川さんを訪ねた時に発見した「数字を適当に言えば曲になる」に従って、車のナンバーを言ったり、ランダムに数字を言って作ったフレーズをもとにしている第1部。 数字を音に変換するなら言葉を音に変換しようと考えた野村が、市川・菊地夫婦の娘さんの言葉(ブーブいきたい、ちいろあおあか、など)を音に置き換えて作った第2部。 林加奈さんが気に入った糸を爪でこすってスライドする奏法による第3部。 片岡祐介さんが目指したおむつがズレ落ちるような情けない世界の第4部。 そして、娘さんが寝静まった後を描いたコーダで終わります。 7 さるう ワークショップで作ったガムランの新曲。本当に音、音楽を突き詰めた後の澄んだ音がそこにあるような気がします。「さるう」は、「サル」が動詞化した言葉か? 「触る」が変化した言葉か?「去る鵜」か?それとも、フランス語の挨拶「salut」の聴き間違いか?それとも、「うるさ」を逆から読んだものか?それとも、「ザウルス」が訛ったものか?諸説あります。大真面目に音になるための儀式のようなものかもしれません。 (文:野村誠) |
|
野村誠 1968年名古屋生まれ。8歳の頃、自発的に作曲を始める。CDブック「路上日記」 (ペヨトル工房)、CDに「Intermezzo」(エアプレーンレーベル)、「せみ」(Steinhand)など。作曲作品に、「だるまさん作曲中」(2001:ピアノと管弦楽)、「つみき」(箏2重奏)など多数。 なかでも「踊れ!ベートーヴェン」、ピアニスト向井山朋子の委嘱による作品「たまごをもって家出する」は有名。 2003年、アサヒビール芸術賞、JCC ART AWARDS(96年)、NEW ARTISTS AUDITION 91(SONY MUSIC ENTERTAINMENT)グランプリ(91年)などを受賞。2003年にはGroningen Jazz Festival(オランダ)での演奏、Ikon Gallery (イギリス)での新作発表、山口情報芸術センター(山口)でのオーケストラコンサー トなどの活動の他、碧水ホールでも「音楽ノ未来・野村誠の世界」ワークショップとコンサート、ガムラン楽舞劇「桃太郎」(マルガサリと共作)を上演した。 ●プレイベント映像上映会の上映作品が変更となりました。 「ポンジョンの崖」に代わって、同シリーズの中から「ドゥスン・ゲダレンの畦道」を上映いたします。 ●先週の土曜日から市民の参加による『音楽ノ未来・野村誠の世界』ワークショップがスタートしました。 『野村誠の日記』ではご本人の文章でその様子が紹介されています。 http://d.hatena.ne.jp/makotonomura/ ●水口ガムランプロジェクトのホームページでは、昨年のプログラム、野村誠『年表』などが公開されています。 http://www.jungle.or.jp/ sazanami/gamelan/title/3-2.htm |
柏木 陽 1970年東京生まれ。93年、演劇集団「NOISE」に参加し、演出家・劇作家の故・如月小春とともに活動を続け、ワークショップ指導の経験を積む。毎年夏に行われる兵庫県立こどもの館のワークショップでは、中高生との野外移動劇の創作のみならず、地域の教育関係者らを対象にした演劇指導者養成講座も行っている。また、毎年春に行われる世田谷パブリックシアターの「中学生のためのワークショップ演劇百貨店」では、脚本から、衣裳、小道具、舞台装置にいたるまで、中学生の発案による手作りの表現を模索している。俳優としての主な出演作品は、「A・R」など93年以降の劇団NOISEの各作品、「ミュージカル・アニー」明治生命(99年)ルースター役、「3年B組金八先生」TBS(02年)、遠山医師役。 現在NPO法人演劇百貨店代表。 片岡祐介 1969年生まれ。10歳くらいから即興演奏や作曲に興味を持ち、木琴やピアノのデタラメ演奏をおこない始めた。東京音楽大学打楽器科に入学するが、音大での音楽に違和感をおぼえ、中退。その後、商業音楽、現代音楽などの分野で、打楽器奏者として活動。97年より3年間、岐阜県音楽療法研究所で、音楽を担当する研究員として勤務。障害者と音楽をすることに夢中になる。 現在、フリーの音楽家。作曲作品に「月」(卓上木琴、鉄琴と鍵盤ハーモニカ)2001、「サボテン島」(マリンバとピアノ)1996等がある。 野村幸弘 1961年、京都市生まれ。東北大学大学院博士課程中途退学。1985〜87年イタリア政府給費生としてシエナ大学に留学し、イタリア美術史を学ぶ。現在、岐阜大学教育学部助教授。 1994年、美術評論「聖なる空間を求めて」が箱根彫刻の森美術館公募論文で佳作入選。同年、アーティスト集団「幻想工房」を結成、構成、振り付け、演出を担当。 2000年、「草原の音楽」が第22回東京国際ビデオフェスティバル・ゴールド賞を受賞。「岐阜大学芸術フォーラム」を毎月1回開催し、さまざまなジャンルのアーティストとともに「場所の芸術」を追求。2002年、片岡祐介・由紀とのコラボレーションによる映像作品「場所の音楽」が、キリンアートアワード2002奨励賞を受賞。 2003年、「水辺の音楽」が水の惑星映像祭奨励賞を受賞。立体オブジェ作品を中心とした「野村幸弘と幻想工房の世界」(岐阜・ギャラリーなうふ)を開催。作曲家山辺義大との幻聴音楽会、作曲家野村誠、坂野嘉彦との映像プロジェクトをはじめ、「場所」をキーワードに、絵画、写真、デザイン、オブジェ制作など、多岐にわたる創作活動を展開している。 |
市川 慎 秋田県生田流箏曲『清絃会』三代目家元足達清賀の息子として生まれる。 高校卒業後、沢井忠夫、一恵両師のもとに内弟子として入門。沢井一恵師、比河流師に師事。 沢井箏曲院講師試験において実技首席合格。 1996年『二十歳のコンサート』を皮切りに毎年秋田市にてリサイタルを催す。 1999年イタリア、ウルビーノ市において親善演奏。 平成11年度文化庁芸術インターンシップ研修員。 同年秋田市芸術選奨を最年少で受賞。 第7回長谷検校記念全国邦楽コンクール最優秀賞、文部科学大臣奨励賞受賞。 NHKテレビ「芸能花舞台」に出演。 第9回賢順記念全国箏曲コンクール銀賞受賞。 平成15年度秋田県芸術選奨を受賞。 現在、東京、秋田を中心に演奏活動、作曲活動を展開。 グループ「箏衛門」「螺鈿隊」「ZAN」メンバー 清絃会副会長 菊地奈緒子 仙台市生まれ、幼少より祖母、母の手ほどきを受ける。 沢井忠夫師、沢井一恵師に師事。 上智大学外国語学部ロシア語学科在学中より『沢井一恵箏アンサンブル』メンバーとして欧州、中南米など、ワールドツアーに参加。リサイタルなどの個人的活動と共に、新作の初演や様々なジャンルの演奏家、アーティストと共に新たな試みの活動を展開。また、第一線のソリストが集まった『沢井忠夫合奏団』、若手箏アンサンブル『箏衛門』と2つの違ったスタイルを持つグループで演奏活動、CDなどもリリースしている。 1999年中国国際音楽会議主催『万里の長城杯』アンサンブルの部2位受賞 2000年度文化庁芸術インターンシップ研修員 長谷検校記念全国邦楽コンクール奨励賞受賞 NHK邦楽技能者育成会第39期卒業 沢井忠夫合奏団団員 秋田県生田流箏曲清絃会会長補佐 http://www016.upp.so-net.ne.jp/naokokikuchi/ |