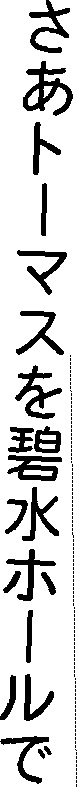プログラム
第1部
マルガサリによるセッション
わたぼうし語り部 伊藤愛子
(休憩)
第2部
おはなし 中川真
『さあトーマス』
たんぽぽの家+マルガサリ
演出 中川真
(大阪市立大学教授・マルガサリ主宰)
出演 たんぽぽの家
(パフォーマンス、ガムラン演奏)
伊藤愛子 奥谷晴美 中西正繁 中村真由美
萩原宏一郎
マルガサリ(ガムランアンサンブル)
中川真 佐久間新 本間直樹 林 稔子
西真奈美 家高洋 河原美佳
美術 森口ゆたか
衣裳 京都造形芸術大学空間演出デザイン学科
教授 中山和子 副手 出口春菜
照明 滝本二郎(エス・アイ・シー)
企画・制作 (財)たんぽぽの家(奈良市)
協力 社会福祉法人わたぼうしの会
|

|
『さあトーマス』における共生の秘訣
この作品は、マルガサリと障害のある人が作りつづけている作品だ。「ともに」つくるというところに特徴がある。コラボレーションという言葉は、英語で collaboration と書く。これを分解すると、col(ともに)labor (骨惜しみすることなく働く)ation(こと)になる。確かに、私たちはどんなところに行き着くのか全く想像だにできずに、ここまでやってきた。少なくともいえるのは、手抜きは全くしていないということだ。だからといって素晴らしい結果になるという保証はない。
『さあトーマス』をつくるというのはかなり特殊な営みだが、ともに何かをつくっているという実感はあり、その方法をずっと模索してきている。もちろん、『さあトーマス』では何を表現するのかということが最大の眼目であり、アートは手段ではなくて目的だと改めてここで言っておこう。共生を目的とする活動ではない。しかし、いかに表現するのかということを腐心する過程で、様々な「共同作業の智恵」を得たことも事実だ。
初めに私が予想していた軌跡は、障害のある人とマルガサリの間にはかなり遠い隔たりがある。それがワークショップを重ねるうちに同化現象が起こり、限りなく近くなるだろう。そして、まるでブーメランのように、やがて再び遠ざかっていくのではないか、というものだ。確証があって考えたものではなく、いわば直感でそう思った。そして、いま確かにそのような軌跡をたどっているように思われる。同化への過程は容易に想像できる。「相手のことが分かりたい」「相手とともに過ごしたい」というポジティブな欲求がある限り、かなえられるだろう。にもかかわらず、再び離れていくというのは、どういうことなのだろうか。
障害のある人とともに作品づくりをするときに、当初にたてた方針は、台本やスコアをつくってはいけない。ましてやそれを彼らに押しつけてはいけない、というものであった。障害のある人の表現を最大限に尊重し、そこから端緒を汲み取ろうというものであった。彼らの表現があまりに強烈で、そうせざるを得なかったし、逆にいえば、それほどの強烈さを持ち合わせていない私たちが一歩引かざるを得ないのであった。
私はまず「同化」を試みた。こちらから近づいていこうという気持ちがある限り、それは可能なのではないかという前提のもとでだ。確かに、ワークショップを積めば積むほど、私たちは親しくなっていったし、確かな信頼関係も生まれた。作品を共同でつくるためのワークショップとは、作品本体をつくるというよりは、まずは信頼関係をつくる場なのであり、それ優先すべきだという思いに達している。1回限りの共演ではなく、今後長くつき合うことが予想される場合はなおさらだ。
しかし、かなりの信頼関係を手に入れてもまだ、実際のところは、同化は危ういと思っている。もちろん、共生と同化は異なる。他者(障害のある人)のできる限り近くにいて、その人の感じ方や感覚、息づかいを知りたいと思うのは自然なことだ。それが共生への自然な道筋だと思うが、困難さを感じるのは、障害のある人たちの「本当の気持ち」がよく分からない点にある。そこに生じている「共生」は、私が語り、解釈する共生に過ぎないのかもしれない。彼ら自身が、本当に「自分らしさ」を保ちつつ、私とともにポジティブにあるのか・・・。その確証を彼らから引き出すことは難し
|